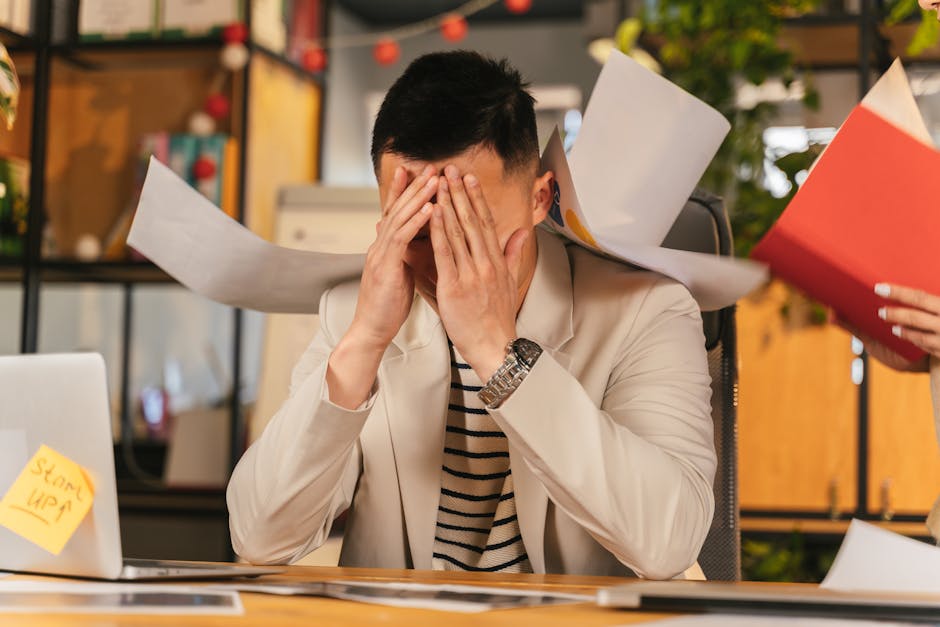中国の巨大ゲーム企業で働く派遣社員たちが直面する過酷な現実が明らかになりました。残業は当たり前、福利厚生は対象外、正社員との間に引かれる明確な線引き――。彼らはプロジェクトの「消耗品」として扱われ、その経験は「優秀な派遣社員であること」しか証明しないと言います。大手企業を陰で支える彼らの日常と、その背景にある「人力差益」ビジネスの実態に迫ります。
「外人」として扱われる派遣社員の日常
中国のゲーム大手企業で2年半勤務し、ほとんど毎日残業していた「馍馍(モモ)」さんの事例は、派遣社員が直面する過酷な労働環境を象徴しています。通常は夜11時まで、プロジェクトの進行が逼迫すれば深夜2時まで働くことも珍しくありませんでした。しかし、正社員とは異なり、遅刻や早退といった柔軟な勤務は認められず、どれだけ遅くまで残業しても翌朝10時半には定時に出社が求められます。
見えない壁と過酷な労働環境
社内コミュニケーションツールでは、派遣社員は本名しか使えず、プロフィール写真も証明写真に限定されます。一方、正社員はニックネームや私的な写真が許されています。入退社時のゲートでは、正社員には「ありがとう」という音声が流れるのに対し、派遣社員には機械的な開閉音のみ。社員証の色も異なり、遠くから見ても一目でどちらが派遣社員か分かるといいます。社内ネットワークへのアクセス権限も厳しく制限され、会社支給のPCと社内ネットワーク環境でしか仕事ができないため、未完了の仕事があれば週末も出社して残業するしかありません。正社員であれば、こうした制限は一切ないのです。
福利厚生の欠如とコミュニケーションの障壁
派遣社員は、大手企業の福利厚生のほとんどから排除されています。阿梅(アメイ)さんの経験によれば、派遣社員時代の給与は同じチームの正社員の3分の1に過ぎませんでした。年次パーティー、チームビルディング、祝日ギフト、部署の食事会といった社内イベントにも参加できず、唯一享受できるのは「たまたまオフィスで提供されるおやつに便乗すること」程度です。
また、運営部門で派遣として働く依依(イイ)さんは、業務に必要な権限申請と承認に多くの時間を費やしています。優先順位が低いため、上司に何度も催促する必要があり、業務の進行が停滞することも頻繁です。重要な会議には呼ばれず、業務関連のチャットグループにも追加されないことが多いため、チームの一員でありながら、重要な情報から隔絶される状況が常態化しています。
「非核心」業務と成果への無関心
派遣社員に割り当てられる仕事は、一般的にプロジェクトの核ではない、実行性が高く、繰り返しの多い業務がほとんどです。イラストレーターの黒子(ヘイズ)さんは、より技術力の高い正社員が人物の主体を描く一方、自分は背景や細部のテクスチャを担当することが多く、自分の仕事が「見えない」と感じていました。
依依さんの上司は、データ整理を自動化する技術的な手間を嫌い、依依さんに手動で作業させることが常でした。依依さんが技術的サポートを求めても、上司は「技術が全てやってしまえば、君の存在意義は?」と冷たく突き放したといいます。このような環境では、派遣社員の労働成果に対するフィードバックもほとんどなく、依依さんは自分の仕事の価値や達成感を全く感じられませんでした。
主管たちはチームの調和と派遣社員のモチベーション維持のため、時に励ます言葉をかけますが、実態は異なります。依依さんが年末賞与について尋ねると、主管は「私の管轄外なので、派遣元の人事に確認してほしい」とあっさり突き放したそうです。また、入社時に「1年後に優秀な成績を収めれば正社員になれる」と持ちかけられた阿梅さんですが、結局、退職するまで正社員になった派遣社員の事例を見ることはありませんでした。
「人力差益」が生み出す現代の搾取構造
2019年頃から、インターネット大手企業の間で派遣(外派)という雇用形態が定着し始めました。特に2022年の「インターネット業界の冬」以降、「コスト削減と効率化」の波の中で、この雇用形態が広く採用されるようになります。
コスト削減と柔軟な人員調整の切り札
サービス型ゲームや大規模オープンワールドゲームの増加に伴い、ゲームプロジェクトは周期的な性質を持ち、人員ニーズが大きく変動します。派遣モデルを利用することで、企業はプロジェクトチームを迅速に拡大・縮小できるため、柔軟な人員調整が可能となります。また、ゲーム開発の「パイプライン化」と「工業化」を追求する大手企業にとって、多くの「労働者」が必要とされており、派遣社員はそのニーズを満たす上で不可欠な存在となっています。
大手派遣会社の人事担当者である楊欣(ヤン・シン)氏によると、派遣モデルの最大の利点は「プロジェクト終了後、大手企業は従業員を解雇する際に、いかなる補償金も支払う必要がない」ことだといいます。
派遣会社の巧妙な利益メカニズム
「商売とは差益を稼ぐことだ」と楊欣氏は語ります。例えば、大手企業があるポジションに対して月2万元(約40万円)を支払うとします。しかし、派遣会社が従業員に支払う給与や社会保険などの総コストが1万2000元(約24万円)だとすると、残りの8000元(約16万円)が派遣会社の粗利となります。これにより、一人の派遣社員から40%もの利益率を生み出すことが可能です。
大手企業は通常、派遣社員に日当で賃金を支払いますが、派遣会社は月給制で従業員に支払います。楊欣氏は、大手企業が派遣社員に支払う日当は本人には厳重に秘密にされ、この差益が派遣会社にとっての利益となることを明かしています。派遣会社の人事担当者のKPIも、担当するグループ全体の利益率と連動しているため、従業員のコストが低ければ低いほど利益は高くなります。
派遣会社は従業員を初級、中級、上級、最上級の4段階に分け、初級社員からの差益が派遣会社の主要な収入源です。かつて派遣会社の人事を務めていた黒子さんも「派遣会社は従業員の給与から一部を搾取する。その程度は良心次第だ」と証言しています。
キャリアパスの閉ざされた未来
楊欣氏の8年間のキャリアの中で、派遣社員が自ら昇給を申し出るケースは稀でした。派遣社員が退職を申し出た際、人事担当者は3回引き留める義務があり、その中には昇給提示も含まれますが、通常は利益率10%の警戒線を超えることはありません。数日休むだけで利益が逆転するリスクがあるためです。
派遣会社の人事担当者もまた、大きなプレッシャーに直面しています。今年3月、米娅(ミア)さんは派遣会社の人事として入社後1ヶ月で、一人も派遣社員を募集できなかったため解雇されました。彼女が直面したのは、派遣という雇用形態に対する警戒心と抵抗感が高まる社会状況でした。求人サイトで積極的に声をかけても応募は少なく、派遣だと分かるとすぐに興味を失う人がほとんどでした。社長に採用の困難を訴えても、「それは君の問題だ」と、話術や説得力の不足を指摘されたといいます。現在、大手企業の正社員人事として働く米娅さんは、募集できないのは能力の問題ではなく、単純にその派遣ポジションがあまりにもひどかったからだと考えています。
まとめ
中国ゲーム大手の派遣社員問題は、急成長するテック業界が抱える構造的な課題を浮き彫りにしています。コスト削減と効率化の名の下、労働者の尊厳が「消耗品」として扱われる状況は、果たして持続可能なのでしょうか。日本企業においても類似の派遣・契約社員問題は存在しますが、中国の事例はより鮮烈な形で、現代社会における労働の価値と、企業倫理について深く考えさせられます。グローバル化が進む現代において、企業は短期的な利益だけでなく、持続可能な雇用環境と、労働者のウェルビーイングをいかに確保していくかが問われていると言えるでしょう。
元記事: chuapp
Photo by ANTONI SHKRABA production on Pexels