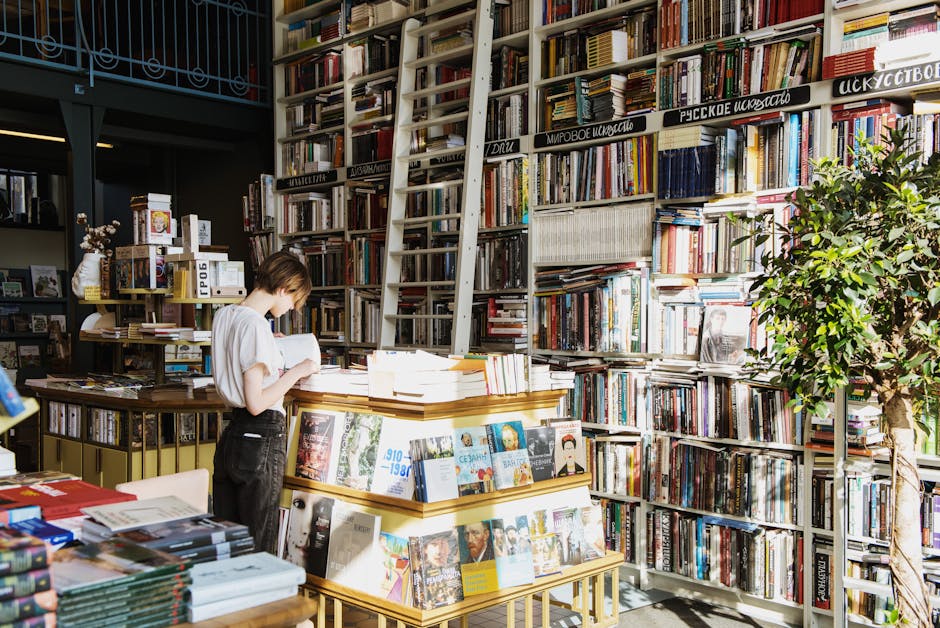近年、中国の主要都市では、日本の「蔦屋書店」をはじめとする洗練された高級書店が、おしゃれな「映えスポット」として大きな注目を集めてきました。しかし、つい最近、中国西南部の旗艦店である「蔦屋書店 成都仁恒置地広場店」が閉店を発表。西安、上海、天津に続き、閉鎖される中国国内の店舗は4店舗目となります。この相次ぐ閉店は、高級書店のビジネスモデルの限界を露呈しているのでしょうか?本記事では、この動向から、高級書店が今後どのように「長く愛される場所」へと進化していくべきかを深掘りします。
中国で進む蔦屋書店の苦境
「インタフェースニュース」の報道によると、蔦屋書店 成都仁恒置地広場店は「会社業務の調整のため」、2025年8月31日をもって営業を終了すると発表しました。同店は2022年8月に開業した、蔦屋書店にとって中国で6番目、西南地域初の店舗であり、成都で唯一の存在でした。
相次ぐ閉店:中国市場の現実
中国商報の報道によれば、成都店の閉鎖以前にも、蔦屋書店は昨年10月から西安マイコ中心店、上海MOHO店、天津仁恒伊勢丹店の3店舗をすでに閉店しています。蔦屋投資の担当者は、これらの閉店がフランチャイズパートナーの事業調整によるものだと説明しています。現在、公式ミニプログラムによると、蔦屋書店の中国国内の店舗は、閉鎖予定の成都店を除くと12店舗。2020年に杭州天目里に中国初出店以来、中国大陸で合計15店舗を展開してきましたが、そのうち4店舗が閉鎖または閉鎖予定となります。最新の店舗は2024年12月にオープンした無錫恵山映月里店です。
「高級書店」はなぜ人気に?そしてなぜ限界が?
立て続けの閉店ニュースは、多くの人に驚きと残念な思いを抱かせました。蔦屋書店の苦境は、私たちに「高級書店の未来」という根本的な問いを投げかけます。
「第三の空間」としての魅力とSNS戦略
蔦屋書店に代表される新しい業態の書店が急速に人気を集めたのは、従来の「本を売る」という単一モデルを根本から覆した点にあります。これらは書籍を文化的な媒体として捉えつつ、カフェや軽食、アート展示、クリエイティブマーケットなどを巧みに融合させ、「第三の空間」という独自の立ち位置を確立しました。この複合的な消費体験は、都市に住む人々が求める「スローライフ」や「美意識」に合致しました。人々は単に本を買いに来るだけでなく、紙をめくる感触を味わい、ハンドドリップコーヒーの香りに浸り、作家のサイン会に参加するといった「体験」を求めたのです。SNS時代においては、洗練されたデザイン空間は自然と拡散され、ユーザーによる自発的な投稿が連鎖的に広がり、書店は瞬く間に都市の文化ランドマーク、そして「インフルエンサー経済」の典型的な成功事例となりました。
「インフルエンサー経済」の限界
高級書店は短期間で莫大な注目と投資を集めましたが、私たちが繰り返し指摘してきたように、インフルエンサー経済の本質は「短期的な効果」にあります。「映え」を目的とした消費行動は、新鮮さやSNSでの「ネタ」、審美的な刺激に依存し、その背後には十分な顧客ロイヤリティやリピート購入の動機が欠けています。消費者は一度の「儀式的な体験」にはお金を払っても、同じ空間やサービスに継続的に費用を投じることは稀です。新鮮さが薄れ、SNSでの熱狂が冷め、消費者が理性的な行動に戻ると、見た目の良さや流行に依存していた書店は厳しい経営圧力に直面します。
これは、「インフルエンサーとしての人気」に頼るビジネスモデルが、市場の変動や消費者の飽きという二重の衝撃に耐えにくいという深い市場法則を反映しています。単なる「来客数」を「固定客」に転換できず、安定したリピート購入の仕組みや長期的な消費関係を構築できなければ、書店の持続的な経営は「水の無い源泉」「根の無い木」となってしまうのです。
「長く愛される書店」になるために
「インフルエンサーモデル」の光が徐々に薄れる中、真に考えるべきは、一時的な人気から「長く愛される存在」へと移行し、持続可能なビジネスモデルを構築する方法です。本当に優れた書店の核となる競争力は、単なる空間デザインや雰囲気作りにとどまらず、「本そのもの」の価値、つまり質の高い選書、専門的な知識サービス、そして深い文化交流を通じて、真に読書を愛する顧客層を惹きつけ、定着させることに回帰すべきです。
「本」本来の価値とコミュニティの重要性
具体的には、書店は独自の審美眼と専門的な深みを持つ選書システムを構築し、多様な興味やレベルの読者に対し、的確な読書案内や新たな知識との出会いを提供できるべきです。同時に、書店は都市の公共文化生活の積極的な参加者となり、定期的な読書会、著者トーク、文化講座、アート展示といった質の高い文化イベントを通じて、安定したコミュニティを形成し、顧客のロイヤリティを高める必要があります。さらに重要なのは、ポイント制度や限定イベント、パーソナライズされたサービスなどを通じて、「会員制」や「コミュニティ化」された運営モデルを構築し、顧客の帰属意識と忠誠心を高めることです。
欧米・日本の小規模書店の事例から学ぶ
例えば、欧米諸国や日本の街角に佇む小さな個人書店を思い浮かべてみてください。そこには豪華な装飾はなくとも、店先に置かれた数席の小さなテーブルで、店主と顧客が本の話題で盛り上がっている光景が見られます。このような親密な交流は、極めて強い「顧客とのつながり」を生み出し、人々を魅了し、何度も足を運びたくなるような魅力的な空間を作り出しています。
書店の未来を考える
長期的に見れば、書店という文化的な業態の未来は、「流行」か「非流行」かという二元論に限定されるべきではありません。むしろ、より多様で深い可能性を探るべきでしょう。「インフルエンサーとしての人気」が薄れることは、書店にとって危機ではなく、再ポジショニングし、本質に立ち返り、差別化された発展を実現する機会なのかもしれません。
未来の書店は、児童書、アートデザイン、人文社会科学、ニッチな文学など、特定のジャンルに深く特化し、特定の読者層にとっての「精神的な故郷」となるかもしれません。あるいは、地域コミュニティ、学校、企業などと深く連携し、文化サービスの境界を広げ、都市の公共文化サービスシステムの一部となる可能性もあります。さらに、「書店+教育」「書店+観光」「書店+デジタルコンテンツ」といった異業種との融合モデルを探求し、新たな価値創出の機会を見出すこともできるでしょう。
したがって、書店の未来は、一時の流行や話題性を追うことにはありません。喧騒とした商業環境の中で、文化という初心を堅守し、価値あるコンテンツとサービスを継続的に提供できるかどうか。それこそが、書店本来の姿であり、私たちが思い描く書店の理想的な未来ではないでしょうか。
元記事: 36氪_让一部分人先看到未来
Photo by Ksenia Chernaya on Pexels