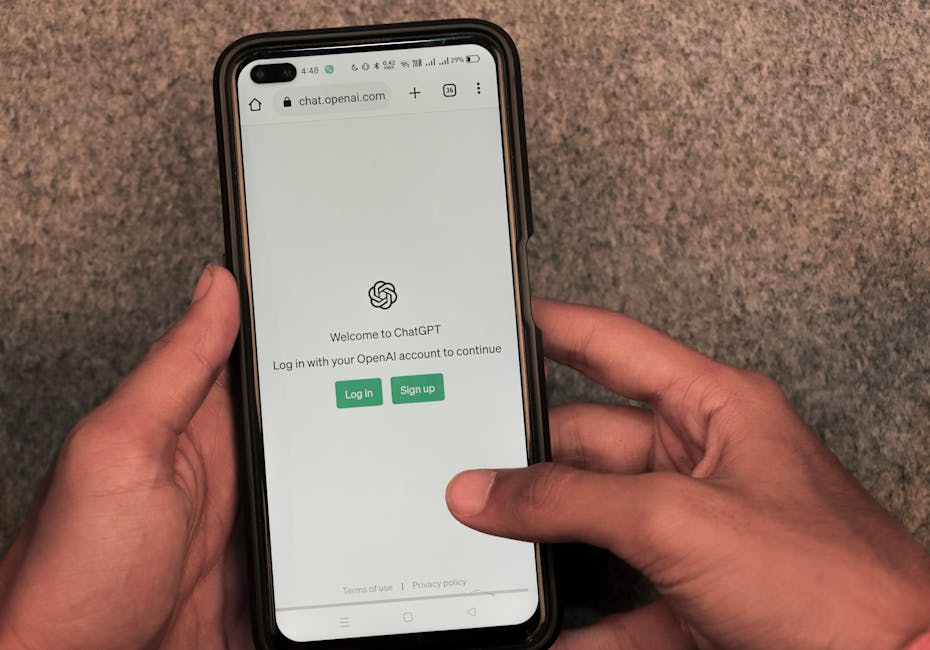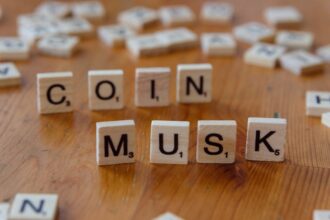「AIはSaaSの成長を加速させる『乗数』だ」――かつてSaaS業界全体がそう信じていました。CRMツールは営業効率の倍増を、コラボレーションツールはチーム生産性の50%向上を謳い、SaaSとAIの組み合わせが無限の可能性を秘めていると期待されたのです。しかし今、この風向きが大きく変わっています。AIが単なる「補助」ではなく、人間が行っていた仕事を直接肩代わりするようになった結果、SaaSは「強化される側」から「代替される側」へと転じているのです。顧客はAIを使って注文記録の処理、レポートの自動生成、さらには基本的な営業活動までこなすようになり、これまでSaaSの成長を支えてきた「席数課金」モデルは、AIによって根本から揺らぎ始めています。これはもはや「乗法」ではなく「減法」の時代。「SaaSからAIを引く」時代が始まり、AIはSaaSの生存基盤を静かに浸食しているのです。
AIがSaaSのビジネスモデルを揺るがす構造的変化
「人中心」から「AI中心」へのシフト:席数課金モデルの崩壊前夜
SaaS業界が過去10年間で享受してきた繁栄は、そのほとんどが「席数課金(ユーザー数に応じた課金)」という柱に支えられてきました。CRMの営業席、コラボレーションツールのチームアカウント、カスタマーサービスシステムの担当者アカウントなど、その本質はすべて「人数課金」です。企業がどれだけの従業員に利用させるかに応じて、費用を支払うというシンプルなモデルでした。このビジネスモデルの根幹にある仮定は、「人がプロセスの中心であり、SaaSは人のためのツールである」というものでした。しかし、AIは今、この根本的な仮定を覆しつつあります。
顧客の「減法」:席数は事業成長に追従しないという現実が浮上しています。最近のBattery Ventureの調査によると、2025年の企業技術予算は全体的に増加するものの、回答企業の76%が「サプライヤー統合」、つまり「より少ないツールでより多くの仕事をこなす」方針を掲げています。さらに厄介なのは、これまで人が操作していた業務プロセスが、AIによって静かに引き継がれつつあることです。
例えば、従業員500人規模の製造企業では、かつてはコラボレーションツールを使って生産スケジュールを管理し、10人のオペレーション専門家が毎日データを更新し、進捗を同期していました。これには10の有料席が必要でした。しかし、AIエージェントを導入した現在、システムは生産設備のデータを自動で取得し、スケジュール表を生成、さらには遅延が発生した場合は警告まで出すようになりました。結果として、10席あった有料席は3席にまで削減され、残った従業員はAIが解決できない異常事態にのみ対応すればよくなったのです。
これは一例に過ぎません。Asanaの経営陣は最近の会見で、「全体のNRR(純収入維持率)が短期的逆風に直面している」と明言しました。その背景は明確です。顧客は従業員の増員をしないばかりか、AIを使って基本的な業務を代替しており、新規席位の購入意欲はどん底に落ちています。「AIを使えば5席分のコストが削減できる」と企業が気づいたとき、SaaSの成長ロジックは「顧客規模の拡大→席位の増加→収入の増加」から、「AIによる効率向上→席位の減少→収入への圧力」へと劇的に変化したのです。
SaaSインターフェースの「冗長化」
さらに危険な兆候として、AIが「SaaSのインターフェース(画面)」そのものの存在意義を失わせつつあります。従来のSaaSのデザインロジックは、「人が操作するための入り口を提供する」というものでした。営業担当者はCRMに顧客とのやり取り記録を入力し、運用担当者はコラボレーションツールでタスクカードをドラッグ&ドロップし、カスタマーサポートはシステム内で顧客の問い合わせチケットを検索する必要がありました。
しかし、AIエージェントの作業モードは「プロセスを直接処理する」ことです。AIエージェントはCRMのインターフェースを介さず、メールや通話記録から直接営業情報を抽出しデータベースに同期させることができます。コラボレーションツールを開くことなく、スケジュールやプロジェクト目標に基づいてタスクプランを自動生成することも可能です。さらに、カスタマーサポートの電話応対やメッセージ返信を代替し、複雑な問題が発生した場合にのみ人間へ引き継ぐ、といった働き方もします。
ある企業のCIOはインタビューでこう断言しています。「もしAIがプロセスの80%を直接完了できるのであれば、なぜ我々は従業員のためにSaaSアカウントを購入する必要があるのか? AIにはインターフェースは必要ない。APIさえあれば十分だ。」これは、SaaSがこれまで依存してきた「ユーザーが必ず自社のシステムを通じて仕事を完結させる」という前提が、AIによって根底から覆されつつあることを意味します。
新たな収益モデルへの挑戦とコストの罠
席数課金モデルの基盤が揺らぎ始めた今、SaaS業界はより困難な問題に直面しています。それは、ビジネスモデルの再構築です。過去10年間、SaaSがもてはやされた核心は、「サブスクリプション制による安定した収入」にありました。一度顧客が料金を支払えば、毎月または毎年安定した収入が見込めるため、事業の予測可能性が極めて高かったのです。しかし、AIはこの「安定した状態」を「変動する要素」へと変えつつあります。
「人数課金」から「効果課金」への移行
「人数課金」から「効果課金」へ――課金ロジックの抜本的な転換が始まっています。2024年末頃から、企業におけるAIの導入に対する姿勢が大きく変化しました。企業はもはや「AI機能があること」に対して支払うのではなく、「AIが生み出す結果」に対して対価を支払うようになっているのです。Gartnerの調査によると、2025年には企業の63%が「AIの実際の使用量や創出された価値に基づいて課金する」ことを明確に求めており、席数課金にAI機能をまとめて含めることにはもはや納得していません。
この変化はSaaSにとって致命的です。もし顧客がAIを活用して5席分の利用を減らした場合、SaaS企業は収入の減少を受け入れるか、あるいは「AIがもたらす新たな価値が、席数減少による損失を相殺できる」ことを証明するかのどちらかになります。しかし後者の証明は極めて困難です。顧客はこう問うでしょう。「もしAIが本当に効率を向上させるなら、なぜ私はもっと多くのお金を払わなければならないのか? むしろコストを削減してくれるべきではないのか?」
Monday.comの事例は典型です。同社は第2四半期決算で売上高が27%増加したことを開示しましたが、「AIが顧客にどのように追加価値を生み出したか」を明確に説明できなかったため、株価が30%も暴落しました。SaaS業界の企業にとって、これは単なる株価の問題ではありません。顧客からの無言の問いかけ、すなわち「貴社のAIはコスト項目なのか、それとも付加価値項目なのか?もし前者なら、なぜ席を減らさないのか?もし後者なら、どのように投資対効果(ROI)を証明するのか?」という本質的な問いに直面しているのです。
AI競争の「コストトラップ」
AI競争における「コストの罠」も顕在化しています。かつてSaaSベンダーは、顧客の疑問に対応するため、「すべての席位でAI機能を無料で提供する」と謳い、AIを無料で「プレゼント」するような状況でした。しかし、これはすぐに儲からない商売だと判明しました。大規模言語モデルのトレーニングコストや、推論段階での計算リソースの費用が、予想をはるかに上回っていたのです。
ある中堅SaaS企業の見積もりでは、10万席のユーザーに無制限のAI機能を提供すると、毎月300万ドルの計算コストが増加し、粗利益の15%が直接食いつぶされることが判明しました。現在、業界では静かに新たなルールが生まれつつあります。AI機能は「席数付加パッケージ」から「従量課金」へと移行し、使用したトークンの量や呼び出し回数に応じて料金が課されるようになっています。
しかし、これは新たな矛盾も生み出しています。Salesforceは最近、顧客からこんな苦情を受けました。「貴社のAIアシスタントのおかげで検索効率が向上し、これまで10回の呼び出しが必要だったタスクが3回で完了するようになりました。なのになぜ、私の請求額は減るどころか増えているのですか?」実は、コストを賄うために、ベンダー側が1回あたりの呼び出し単価を静かに引き上げていたのです。「効率が向上したのに顧客コストが増加する可能性がある」というこの逆説が、AIを「付加価値」から「論争の的」へと変えつつあります。
「自己破壊」か「被破壊」か:SaaS企業の生き残り戦略
これらの変化に対し、SaaS企業が何もしないわけではありません。ServiceNowは「エージェント型AI」を注文エンジンとして活用し、AI関連の大型契約が著しく増加、さらにはAI関連のARR(年間経常収益)比率について明確な目標を打ち出しています。しかし、このような変革は本質的に「自己破壊」を意味します。つまり、自社がこれまで依存してきた席数課金モデルを、新たなAI駆動型モデルで置き換えることを意味するのです。
これには一連の連鎖反応が伴います。営業対象はCIOから事業部門の責任者へと変わります(AIの価値は事業成果に現れるため)。製品設計は「人のためのインターフェース設計」から「AIのためのAPI設計」へと転換します。さらには、組織構造そのものも再構築が必要となります。これまで「機能改善」を担当していた製品チームは、今や「AIエージェントのプロセス設計」を理解し、実行する能力が求められるのです。
最も難しいのは、経営陣の心構えでしょう。過去10年間、席数課金モデルで10億ドルの収益を上げてきた企業が、今になって「席数課金モデルは徐々に縮小する」という現実を認め、不確実性の高いAIモデルにリソースを投入するには、並々ならぬ勇気が必要です。しかも市場は待ってくれません。顧客は席数を減らし、競合他社は「効果課金」のソリューションを次々と発表しており、SaaS企業に残された変革の窓は狭まる一方です。
まとめ
AIによるSaaSへの「ダメージ」は、本質的には業界再構築の産みの苦しみです。これはSaaSを消滅させるのではなく、その定義を書き換えるものにほかなりません。すなわち、「人々にツールを提供する」ことから「プロセスに知的なサポートを提供する」へ、そして「人数に応じて課金する」ことから「価値に応じて課金する」モデルへの転換です。
このプロセスは必ず痛みを伴います。かつてオンプレミス型ソフトウェアからクラウドSaaSへの移行期に多くのベンダーが淘汰されたように、今回の変革期もまた、時代の波に乗れない企業を厳しく選別するでしょう。しかし、これは業界のプレーヤーにとって新たな機会でもあります。いかにAIを自社のコアシナリオと結びつけ、新しい価格設定モデルで価値とコストのバランスを取るかをいち早く見極められる企業こそが、SaaS-AI時代における新たな成長曲線を見出すことができるはずです。技術革命の厳しさは旧秩序を破壊することにありますが、その素晴らしさは、常に新たな強者が廃墟の上に立ち上がる点にあるのです。
元記事: 36氪_让一部分人先看到未来
Photo by Sanket Mishra on Pexels