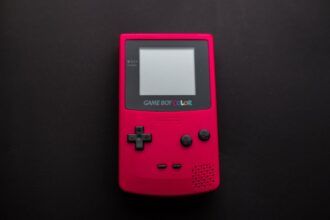2025年8月8日、中国の有力ゲームメディアChuappが独占インタビューを公開しました。話題の中心は、中国のゲーム開発会社・無端科技が4年の歳月をかけて開発し、テンセントがパブリッシングを手掛けるPvEシューター『マトリックス:零日危機』(以下、『マトリックス』)。先日WeGameとSteamで正式リリースされた本作は、開発過程で「メタバース」構想の転換やUnreal Engineへの大胆な技術移行など、多くの困難を乗り越えてきました。プロデューサーCould氏への独占インタビューを通じて、この意欲作がいかにして誕生したのか、その舞台裏に迫ります。
中国産PvEシューター『マトリックス:零日危機』が満を持して登場!
『マトリックス:零日危機』は7月30日にWeGameとSteamで正式にリリースされました。筆者は今年のBilibili Worldで先行体験会に参加し、完成度の高さとスムーズなゲームプレイに驚かされたといいます。特に、ローグライク要素と、20分前後に調整されたプレイ時間が、リプレイ欲を掻き立てる魅力となっていました。しかし、かつて筆者が体験した初期バージョンにあった「ランダム生成ステージ」や、一時期話題を集めた「メタバース」といった概念が、正式版では姿を消しています。なぜこれらの要素は採用されなかったのか? ランダム生成マップは地形の起伏や精細度が不十分で断念せざるを得なかったと説明されました。そして、「メタバース」については、開発チームのCould氏に直接尋ねることで、この4年間でゲーム内外に起きた物語を紐解くことになります。
「メタバース」の光と影:コンセプト転換の舞台裏
立案当初の「メタバース」構想
「チーム内で今も『メタバース』について話しますか?」という筆者の問いに対し、Could氏は率直に「『マトリックス』は『メタバース』を核として立ち上げたわけではありません」と答えました。プロジェクトの誕生は、会社の「シューター+α」戦略の一環であり、「メタバース」はその解決策として導入された「ツール」の一つに過ぎなかったのです。PvEシューターという核となるゲームプレイが決まる中で、Could氏らは、いかにして統一された世界観の中で多様なコンテンツを合理的に追加していくかという課題に直面していました。
そんな中、「メタバース」がブームとなっていた時期にプロジェクトが立ち上がります。Could氏は、『レディ・プレイヤー1』に登場する「オアシス」のように、荒廃した世界、サイバーパンク、異星、あるいは童話のような世界観まで、あらゆるものを許容できる「容器」として「メタバース」を捉えていました。これにより、世界観の整合性に悩むことなく、クリエイターは自由な発想でコンテンツを制作でき、将来的な大規模なコンテンツ更新にも対応できると考えたのです。さらに、将来的なIPコラボレーションにおいても「メタバース」の枠組みは非常に有効だとCould氏は指摘しています。実際、『マトリックス』では今年、大規模なコラボレーションを予定しているとのことです。
市場の変化と「メタバース」の脱却
しかし、市場の風向きは急速に変わります。『マトリックス』が初めてパブリッシャーであるテンセントにデモを見せた頃には、「メタバース」という言葉は、かつての流行語ではなくなっていました。Could氏によると、ブームの直後から「メタバース」はNFTやブロックチェーンといった投機的なイメージと結びつき、負の連想が強まっていたといいます。長期的な運営を目指すゲームにとって、こうした負のイメージは致命的です。開発チームは「メタバース」を実用的な目的で利用していることを明確に説明できたとしても、その機会はほとんどないだろうと判断しました。結果として、プロジェクトの企画書で輝いていた「メタバース」という言葉は、マーケティング上避けるべき「地雷」へと変わっていったのです。最終的にチームは、このラベルをあえて薄めることで合意し、「多元宇宙」や「パラレルワールド」といった、より中立的な表現へと置き換えられました。
「シューター+α」戦略:ニッチ市場への挑戦とUnreal Engineへの転身
ニッチ市場「PvEシューター+ハクスラ」の開拓
「メタバース」の光が薄れる中、『マトリックス』の真の目標はより明確になりました。それは、流行を追う概念的な製品ではなく、チームが長年計画してきた戦略的な製品としての「シューター+細分化領域」です。Could氏は、「レッドオーシャン(競争が激しい市場)には直接参入しない」と語り、同時期に断念された『Escape from Tarkov』のような「探索・戦闘・撤退」を基本とするエクストラクションシューターの開発について触れ、競合との差別化の難しさを理由に挙げています。
『マトリックス』が目指したのは、まだ市場が十分にカバーされていない「シューター+PvE」、さらに具体的には「シューター+ハクスラ(刷子ゲーム)」というニッチな市場でした。純粋なPvEシューターは相対的に少なく、ここにブルーオーシャンを見出したのです。PvEモードを好むシュータープレイヤー、そしてローグライクやハクスラゲームのファンを取り込むことを目標としています。これは、無端科技が大手企業と開発力やマーケティングで対抗できないため、特定のゲームプレイやコンテンツ更新速度で優位性を築く戦略でもありました。ビジネスモデルは「2A(AAAではないが一定規模の)+オンラインゲーム」と位置付けられ、数値バランスに影響しないスキンや外観の販売を収益の柱としています。
Unreal Engineへの戦略的移行
『マトリックス』の開発に約4年を要したのは、単にゲームを成功させるだけでなく、会社全体のUnreal Engine(アンリアルエンジン)への技術転換という、もう一つの重要な使命を背負っていたからです。Could氏はこれを無端科技の「戦略的任務」であり「歴史的使命」と表現しています。
それまで同社の主力エンジンはUnityでしたが、プロジェクトの複雑化に伴い、その限界が浮き彫りになっていました。Could氏は、別のゲーム『生死狙撃2』での経験を例に挙げ、Unityを魔改造するために膨大な時間を費やし、Unreal Engineでプラグインを使えば3日で済むような機能を、Unityでは3ヶ月かけて基盤ツールから構築する必要があったと振り返ります。このメンテナンスだけでも年間数千万元(日本円で数億円)のコストがかかっていたというのです。このような持続不可能な状況から、Unreal Engineへの移行を決断。『マトリックス』はその先鋒となり、ゼロからUnreal Engineのワークフローを構築し、新しいチームを組織するという、製品開発以外の大きなプレッシャーを抱えてプロジェクトがスタートしました。Could氏の記憶では、当初は彼一人から始まり、コアメンバーの募集からチームの立ち上げ、そして定着まで2年以上を要したといいます。
この技術転換の最大の恩恵は、コンテンツ制作効率の大幅な向上です。Unreal Engineのブループリントシステムが、その効率化に大きく貢献しています。
まとめ:中国ゲーム開発の新たな挑戦
『マトリックス:零日危機』は、単なるPvEシューターゲームとしてだけでなく、中国ゲーム開発の進化を示す象徴的なプロジェクトと言えるでしょう。市場のトレンドに左右されず、自社の強みを生かした「シューター+α」のニッチ戦略。そして、Unityの限界を乗り越え、Unreal Engineへの大胆な技術移行を決断した無端科技の挑戦は、中国ゲーム業界が単なる模倣ではなく、自律的な技術革新と市場開拓に本格的に乗り出していることを示しています。
一時的に脚光を浴びた「メタバース」のような概念から脱却し、足元のゲームプレイと持続可能なコンテンツ展開に焦点を当てる戦略は、日本のゲーム開発者にとっても多くの示唆を与えるかもしれません。今後、『マトリックス:零日危機』がPvEシューター市場でどのような存在感を示すのか、そしてその技術革新が中国のゲーム産業全体にどのような影響をもたらすのか、注目が集まります。
元記事: chuapp
Photo by cottonbro studio on Pexels