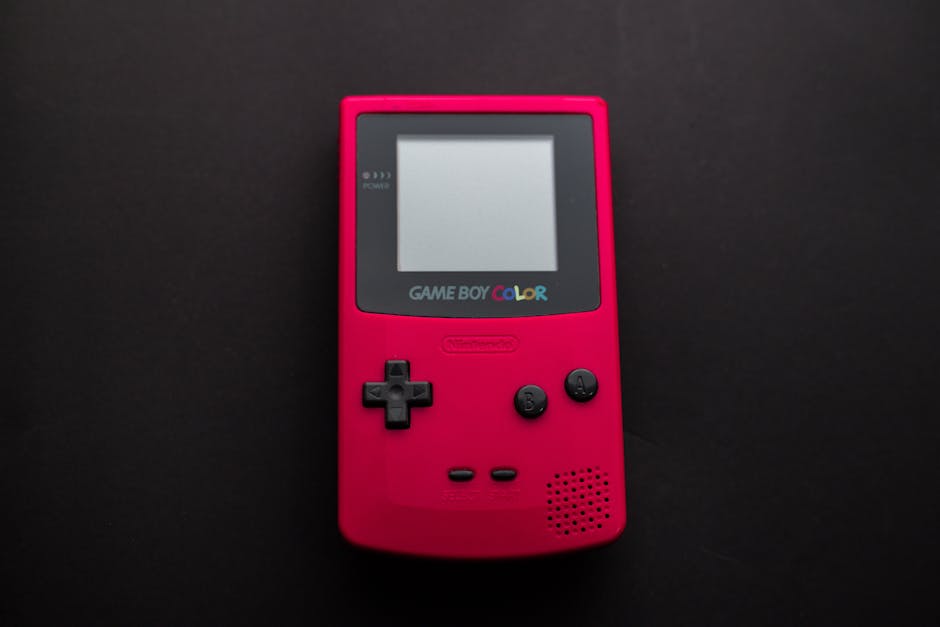先日、セガの往年の名作「スーパー忍」の正統続編となる『スーパー忍:反攻の斬撃』がSteamで発売されました。1989年のメガドライブ版から実に36年ぶりの新作登場は、往年のファンにとって待望のニュースでしょう。しかし、この新作を機に、セガが抱える「IPの世代間ギャップ」という課題が浮き彫りになっています。かつては任天堂と並び称されたゲーム界の巨人が、なぜマリオやリンクのような普遍的な人気を得られなかったのか。その背景には、セガの激動の企業戦略とIP育成の難しさがありました。
懐かしの「スーパー忍」復活!しかし立ちはだかる世代の壁
8月29日、『スーパー忍:反攻の斬撃』がSteamストアに登場しました。筆者もBilibili Worldのセガ新作発表会で試遊しましたが、現代において発売されるとは思えないほど純粋な2D横スクロールアクションゲームで、まさに1989年のメガドライブ版『スーパー忍』の正統な続編と言える出来栄えです。前作『Shinobi』(PS2)からは20年以上が経過しており、このクラシックIPが再びプレイヤーの前に現れたことは、ある種のロマンティックな継承と言えるでしょう。
しかし、世間の熱気を比較すると、任天堂の「マリオ」IPほどの盛り上がりは見られません。1990年代、セガと任天堂はゲーム業界の二大巨頭であり、「ソニック」の影響力はマリオに引けを取りませんでした。しかし30年以上の時が過ぎ、任天堂のキャラクターが何世代にもわたる共通の記憶となっている一方で、セガのクラシックIPは若い世代の認知から大きく断絶してしまいました。今の若いゲーマーはマリオやリンクを知っていても、ソニックには疎く、ましてや「忍」シリーズの主人公「武蔵」を知る人は少ないでしょう。
実際に、ゲームをしない友人に「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を知っているか尋ねたところ、「聞き覚えはあるが思い出せない」という人や、「全く知らない」という人もいました。対照的に、彼ら全員がマリオを知っており、「配管工」という職業まで即座に答えられるほどです。この認知度の差は、セガIPが抱える大きな課題を物語っています。
セガIPの認知度低下の背景:不安定な企業戦略とハード事業の撤退
セガIPが若い世代に認知されない原因の一つは、その「不安定さ」にあると筆者は考えています。任天堂は一貫してハードウェアとソフトウェアの両方を製造する会社です。このモデルは、閉鎖的でありながら安定したエコシステムを構築しました。優れたゲームがハードの売上を押し上げ、ハードの成功が次世代ゲームのための強固なプラットフォームを提供する。この好循環が、任天堂のIPに安穏な家を与え、世代を超えて成長し続ける基盤となりました。
一方、セガの道のりは波乱に満ちていました。1988年にメガドライブを発売後、時代に合わせてメガCDやスーパー32Xといった周辺機器を次々と投入し、さらにセガサターン、ドリームキャストと独自のハードウェア戦略を展開しました。この比較的混乱したハードウェア戦略は、プレイヤーと開発者の双方のエネルギーを分散させました。ユーザーはどのハードを買えばいいのか分からず、開発者もどのプラットフォームにリソースを投入すべきか確信が持てなかったのです。IPの成長には安定した環境が必要ですが、セガのハード戦略はそれを提供できませんでした。ハードウェアの失敗は、その都度IPの根幹を揺るがす結果となったのです。
そして2001年、セガは大きな決断を下します。ハードウェア市場からの撤退と、純粋なソフトウェア開発会社への転身です。これはビジネス上の生き残り策でしたが、自社IPの価値には大きな打撃を与えました。ソニックはもはやセガのハードと紐付けられることはなくなり、プレイヤーがハードを購入する理由ともなり得なくなりました。セガのIPは、かつての競合である任天堂やソニーのゲーム機など、さまざまなプラットフォームで展開されるマルチプラットフォームゲームの一つへと変貌したのです。独占という輝きが失われ、セガの看板IPは「あれば選択肢の一つ」という位置づけに格下げされました。この立ち位置の変化がブランドの独自性を希薄化させ、IPと本来のプラットフォームとの共生関係を断ち切ったと言えるでしょう。
ソニ「ック」と「忍」シリーズの苦難
企業基盤の不安定さは、製品品質のばらつきに直結しました。ソニックが2Dから3Dへと移行した際、1998年の『ソニックアドベンチャー』は壮大な構想を持っていたものの、実際の完成度は問題が多く、わずか2年前に発売されほぼ完璧と評価された『スーパーマリオ64』と比べると、その差は歴然でした。以降、「ソニック」シリーズの品質はジェットコースターのように乱高下します。特に2006年の『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』(通称「Sonic ’06」)は、拙速な開発によって数多くのバグと粗悪な品質で発売され、ブランドの評判を著しく損ねました。一度失われたプレイヤーの信頼を再構築するのは非常に困難です。懐古的な感情を持たない新しいプレイヤーにとって、品質が安定しないシリーズは、当然ながら魅力的ではありません。
「忍」シリーズの消滅は、不安定な企業がいかにIPを蝕むかを示す、より明確な例です。1980年代の忍者ブームの中で誕生し、アーケードやメガドライブ時代にはトップクラスのアクションゲームとして君臨しました。しかしブームが去るとともに、セガはこのIPに継続的な注目を与えることはありませんでした。シリーズは頻繁に主人公が交代し、コアキャラクターの魅力を希薄化させ、作品の品質も一貫せず、プレイヤーからの評価を消耗していきました。セガ自身が苦境に陥る中で、「忍」のような丹念な作り込みを要するIPは、育つ土壌を失い、次第に市場とプレイヤーから忘れ去られていったのです。
任天堂のIP戦略との対比:品質へのこだわりと多角的な展開
対照的に、任天堂のIP戦略は今から見れば驚くほどの先見性を持っていました。「マリオ」や「ゼルダ」シリーズは、一つ一つのコア作品のリリースに極めて慎重で、品質を保証するためなら数年の延期も厭いません。この品質への徹底したこだわりが、任天堂に消費者の信頼を勝ち取らせ、「信仰に似たファン」を生み出しました。さらに言えば、任天堂はIPライセンス、映画、テーマパークといった多角的な展開によって、クラシックIPを「出圈(一般層への浸透)」させています。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにある「スーパー・ニンテンドー・ワールド」はその象徴と言えるでしょう。
まとめ
結局のところ、セガIPのファン層の断絶は、安定性と忍耐の問題に帰結します。長年にわたる企業運営の混乱の中で、セガのIPは安心して成長できる拠り所と、継続的な品質保証を失ってしまいました。近年、「ソニック」が映画によっていくらか人気を取り戻したとはいえ、それは長年存在した世代間の裂け目を修復しようとする、遅すぎる弥縫策(びほうさく)に過ぎないのかもしれません。
しかし、今回の「スーパー忍」の復活は、セガが再び自社のレトロIPに目を向け、その価値を現代に再構築しようとする意欲の表れとも受け取れます。過去の過ちから学び、今後どのようにIPを育成し、新しい世代へと繋いでいくのか。セガのこれからのIP戦略に、日本のゲーマーも大きな期待を寄せていることでしょう。
元記事: chuapp
Photo by Luis Quintero on Pexels