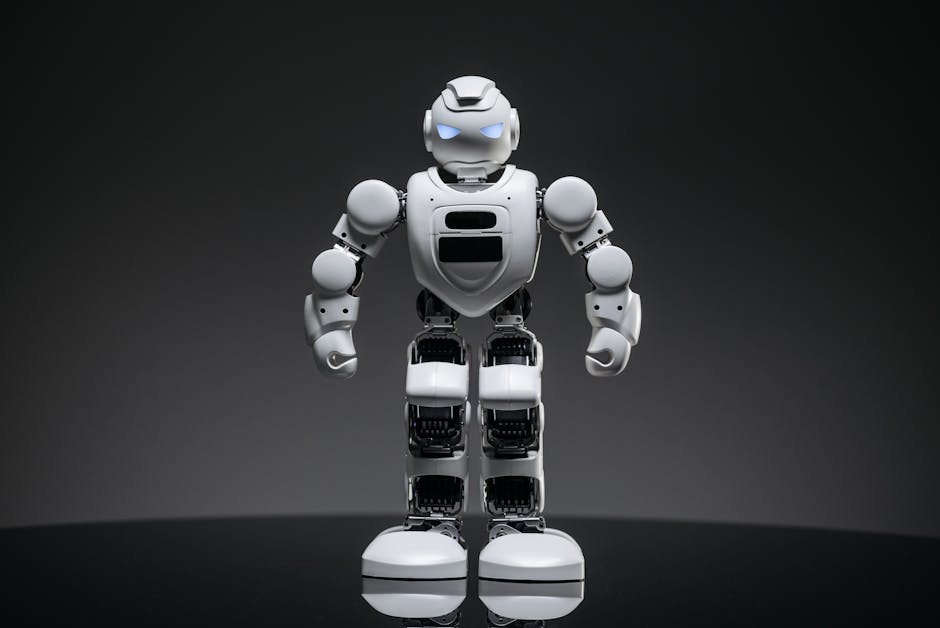中国の最先端ヒューマノイドロボット「Unitree Robotics(宇樹ロボット)」の「H1」が、まさかの「人身事故」を起こしたとして、世界中で大きな話題になっています。まるでSF映画のワンシーンのように、ロボットが人を「衝突・逃走」したと報じられ、YouTube、Reddit、X(旧Twitter)など各SNSで動画が拡散。多くの人々が、アンドロイドが人類を脅かす未来に不安を覚えたかもしれません。しかし、この衝撃的な事件の背後には、意外な「真相」が隠されていました。今回の騒動をきっかけに、急速に進化するヒューマノイドロボットの現状と、その未来について深掘りします。
「衝突騒動」の真相とロボット運動会の熱狂
世界を騒がせた「まさかの出来事」
「アシモフのロボット三原則」が頭をよぎるような、衝撃的な映像でした。競技中のロボットが人を避けずに衝突し、そのまま走り去る姿は、見る者に「まさかロボットが人類に危害を加えるのか?」という不安を抱かせました。一部からは、「三原則の第一条(人間に危害を加えてはならない)に違反したため、即刻破壊すべきだ」という過激な意見まで飛び交ったほどです。
しかし、この「H1」は、首回ロボット運動会の1500m走で6分34秒という世界記録を樹立し、見事金メダルを獲得しています。これは人間世界記録(3分26秒)には及ばないものの、ロボットとしては驚異的な速さです。競技中には、あまりの速さに他のロボットを周回遅れにするほどのパフォーマンスを見せつけたといいます。そんな高性能ロボットがなぜ、衝突事故を起こしてしまったのでしょうか。
「犯人」は人間?リモコン操作の舞台裏
詳細な分析が進むにつれて、「衝突」の原因はロボット自身ではなかったことが明らかになりました。実は、衝突が起こる直前、2人の人間オペレーターがリモコンの引き継ぎを行っていたのです。その際、彼らは前方に人がいることに気づかず、適切な回避指示をロボットに送ることができませんでした。つまり、この「衝突・逃走」事件は、人間側の操作ミスが引き起こしたものだったのです。
「なぜ、ロボットの競技にリモコン操作が必要なのか?」という疑問が当然湧いてきます。その理由としては、以下の2点が挙げられます。
- ロボットの動的バランスの問題:高速での「走る」という動作は、ロボットにとって極めて不安定な運動です。現状のセンサー、アルゴリズム、アクチュエーターの反応速度や精度では、複雑な地形や予期せぬ状況に自律的に対応しきれない場合があります。人間によるリモコン操作は、ロボットがバランスを崩しそうになった際に、リアルタイムで介入し、転倒を防ぐ役割を果たします。実際、Unitreeの別のロボット「G1」は、今年4月のロボットハーフマラソンで転倒する場面もありました。
- 環境認識の不足:センサーは環境情報を提供しますが、高速走行時にはデータの遅延や精度不足が生じることがあります。ロボットは人間のように、瞬時に周囲の状況を判断し、危険を回避することがまだ難しいのです。人間がリモコンで操作することで、この自律認識の不足を補っています。今回のH1の事例も、一時的にリモコン操作が途切れたことで衝突が発生しており、その点を裏付けています。
もちろん、全てのヒューマノイドロボットがリモコン操作を必要とするわけではありません。今回の1500m走で2位だった北京人形ロボット創新センター開発の「天工Ultra」は、自律走行で参加していました。また、「肇事」の当事者であるUnitreeのH1自体も、基本的な自律運動能力は備わっています。H1は2023年8月に誕生したUnitree初の汎用ヒューマノイドロボットで、身長1.8m、体重47kg。移動速度は毎秒3.3m、潜在的な最高速度は毎秒5m(時速18km)と、驚くべき身体能力を誇ります。
ロボット競技の多様な側面と未来への視点
競技種目で変わる「自律」の定義
ロボット競技における「リモコン操作の必要性」は、その競技が何を重視するかによって異なります。
- 自由格闘技:この種目では、人間がロボットを操縦してパンチやキックを繰り出します。ここでは、ロボットの重心設計がいかに優れているか、相手の強い打撃を受けても倒れないか、といったハードウェア性能が試されます。人間が操作することで、より柔軟かつ迅速な攻防が可能となり、激しい状況下でのロボットの性能を最大限に引き出すことができます。
- サッカー:一方、ロボットサッカーは完全にロボットが自律でプレーします。この競技では、ロボットの「戦略判断能力」や「協調性」が問われます。動きの柔軟性や転倒の頻度はまだ人間に及ばないものの、「いつボールを蹴るか」「いつ相手をブロックするか」「誰が味方で誰が敵か」「チームメイトとどう連携するか」といった判断は全てロボット自身が行います。試合中にパフォーマンスが向上するなど、アルゴリズムの学習能力も垣間見えます。
このように、ヒューマノイドロボットの運動会は、彼らの「脳」(アルゴリズムや戦略)あるいは「四肢」(モーターや関節といったハードウェア)といった、それぞれの単一能力を試す場となっていることが伺えます。
CEOが語る「ロボットの未来」と「誤解」
今回の騒動を受け、Unitree Roboticsの創業者兼CEOである王興興氏がコメントを発表しました。
「金メダルは予想通りでした。今回もH1の最高記録ではありませんし、毎秒5mの最高速度には達していません」と、自社ロボットのポテンシャルへの自信をのぞかせます。また、一部で「黒い噂」が流れたことについても、「ここ数ヶ月、ネット上でひどく中傷されたので、今回の好成績に正直ホッとしました」と、率直な心情を明かしました。
リモコン操作については、「H1にはリモコンなしで動く能力も備わっていますが、速度を追求するため、今回の大会ではリモコン操作を選択しました。オペレーターには負担がかかりますが、次の大会では間違いなく完全自律で走らせます。これは難しいことではありません」と、次回の大会での完全自律走行を明言しました。さらに、来年には北京亦庄ハーフマラソン(人形ロボットハーフマラソン)への参加も予定していると語っています。
王氏は以前のインタビューで、ロボットが「問題」を起こした際に世間の注目が集まることについて、「ロボットが普通に歩いたり走ったりしている時はあまり注目されませんが、何らかの原因で問題が発生すると、議論が爆発的に増えます」と指摘し、「誰もが新技術や新製品に対して、もっとオープンな気持ちを持つべきです。業界には浮き沈みがあるものですが、それを受け入れ、未来への大きな自信とサポートを持つべきだと思います」と、大衆の理解を求めました。
まとめ:進化するヒューマノイドロボット、日本の未来へ
今回のUnitree H1の「衝突騒動」は、一見するとネガティブなニュースに見えましたが、実はヒューマノイドロボット技術の現状と、その進化の途上にある課題を明確に示してくれました。人間による操作ミスが引き金となったとはいえ、高速走行下でのロボットの自律性や環境認識能力がまだ完全ではないことが浮き彫りになりました。しかし、同時にUnitree H1が驚異的なスピードを達成し、CEOが今後の完全自律化を約束したことは、ヒューマノイドロボットが急速に進化している証でもあります。
中国をはじめとする世界のテック企業が開発競争を繰り広げる中、ヒューマノイドロボットは、工場での作業から、物流、そして家庭内サービスへと、その活躍の場を広げていくでしょう。日本においても、少子高齢化が進む中で、ロボット技術への期待は高まるばかりです。今回の「騒動」が、日本の読者にとって、ロボットと共存する未来について深く考えるきっかけとなれば幸いです。ヒューマノイドロボットが真の意味で自律し、安全に人々の生活を支える日が来ることを、私たちは期待しています。
元記事: 36氪_让一部分人先看到未来
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels