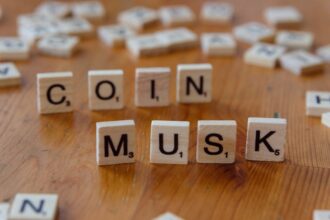AIの急速な普及が、世界の就職市場に激震をもたらしています。特に、かつては高給と安定が約束されていたコンピュータサイエンス(CS)専攻の学生たちが、今やキャリアの第一歩を踏み出すことさえ困難に直面しています。GPAほぼ満点のトップ学生が、2500社に応募してわずか10回の面接しか得られない――この信じがたい現実は、もはや個人の問題ではありません。企業が「即戦力」を求める一方で、AIが多くの入門レベルの仕事を代替する中、新卒たちは一体どこへ向かうのでしょうか?
AI時代の就職氷河期:高学歴CS学生の現実
「世界を変えるコードを書きたい」。多くのコンピュータサイエンス専攻の学生が抱く夢です。しかし、AIが世界を変えたのは、彼らのキャリアパスを奪う形でした。CS専攻の優等生、ケネス・カン氏の経験は、その厳しさを如実に示しています。彼は卒業後、2500件を超える求人に応募したにもかかわらず、得られた面接の機会はわずか10回でした。
大学でChatGPTを使って論文を書いていた学生たちが、まさか自分たちが職場で最初の一歩を踏み出すための「入門レベルの仕事」をAIに奪われるとは夢にも思わなかったでしょう。彼のGPAはほぼ満点、数々の受賞歴を持つ輝かしい経歴の持ち主です。それにもかかわらず、正社員の仕事を見つけることが「贅沢な望み」と化しています。さらに衝撃的なのは、彼の友人の中には、2年間も職を見つけられずにいる人もいるという事実です。
この状況は、世界の厳しい雇用情勢を象徴しています。AIが新卒が本来就くはずだった「初級ポジション」を奪い去る一方で、企業は「即戦力」型の人材を求める傾向を強めています。AIはこのトレンドを加速させ、結果として、従来の人材育成の連鎖が断ち切られ、スキルギャップが拡大しているのです。
カリフォルニア州の雇用統計に見るホワイトカラーの試練
この雇用情勢の厳しさは、特にテック業界が集積する地域で顕著です。本記事が報じられた時点では、カリフォルニア州の失業率は7月に5.5%に上昇し、全米平均の4.2%を上回り、全米で最も高い水準となりました。これは、テック業界をはじめとするオフィス関連職種の低迷が主な要因です。
興味深いことに、製造業や物流業などのブルーカラー経済は回復の兆しを見せています。7月には、貿易、運輸、公共事業部門で1300件、製造業で300件の雇用が増加しました。しかし対照的に、プロフェッショナル・ビジネスサービス分野では7100件、情報技術産業(テック企業が主)では1000件の雇用が失われています。これは、ブルーカラー経済が回復する一方で、ホワイトカラー経済が縮小しているという明確な傾向を示しています。
ドゥアン・モリス法律事務所の顧問であるマイケル・バーニック氏は、AIによる代替も一因としつつ、パンデミック中に過剰に採用した人員の削減が続いていることも、テック業界の厳しい状況の背景にあると指摘しています。
「職場の第一歩」を奪うAI:断絶する人材育成の連鎖
多くの新卒にとって、キャリアをスタートさせるための「第一段階の梯子」とも言える入門レベルの仕事が、AIの波によって奪われています。雇用主はますます新人に対し「即戦力」を求めるようになり、結果として企業の入門レベルのポジションは希少化し、インターンシップの機会さえも減少しつつあります。
ベンチャーキャピタルSignalFireの報告によると、2019年以降、テクノロジー業界の大手15社における新卒採用数は50%以上も減少しています。パンデミック前には、新卒が大手テック企業の採用総数の15%を占めていましたが、現在ではその比率はわずか7%にまで落ち込んでいます。
このような状況は、長年にわたり築かれてきた人材育成の連鎖を断ち切り、深刻なスキルギャップを生み出す可能性を秘めています。従来、新卒は入門レベルの仕事からスタートし、OJT(On-the-Job Training)を通じてスキルを習得し、内部で昇進していくのが一般的でした。しかし、入門レベルの仕事が消失することで、この一連の人材育成パスが分断されつつあるのです。
ロンドン大学キングス・カレッジのステラ・パキディ教授は、伝統的な専門人材の育成方法が完全に消滅し、巨大なスキルギャップが生まれる可能性があると警鐘を鳴らしています。短期的なコスト削減のために入門レベルの採用を削減することは、長期的に見れば、企業の将来的なリーダーシップ層の育成を阻害し、専門性の高い人材不足を招く恐れがあるのです。
まとめ:日本への示唆と未来への展望
AIがもたらすこの雇用市場の劇的な変化は、もはや遠い国の話ではありません。日本においても、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速とAI導入が進む中で、同様の課題が顕在化する可能性があります。
AIの進化は、短期的には一部の雇用を奪うかもしれませんが、長期的には新たな職種や働き方を創出するとも言われています。しかし、その移行期において、個人が直面する困難は計り知れません。私たちは、AIを「脅威」として捉えるだけでなく、それを最大限に活用し、自身の専門性を高める「ツール」として捉え、能動的に対応していく必要があります。
教育システムと企業、そして個々人が、AIがもたらす変革にどう適応していくかが、今後のキャリア形成と社会の発展において極めて重要となるでしょう。リスキリング(学び直し)や、AIと共存する新しい働き方の探求は、喫緊の課題であり、未来の専門人材を育成するための新しい道筋を模索していくことが求められています。
元記事: 36氪_让一部分人先看到未来