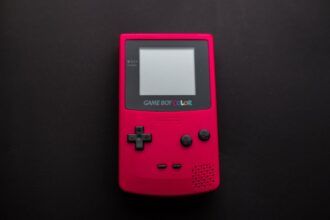中国のゲーム業界で注目を集めていた著作権侵害訴訟に、新たな展開がありました。人気SLGゲーム『三国志・戦略版』(以下、『三戦』)が『率土之濱』(以下、『率土』)から訴えられていた裁判の二審で、衝撃的な逆転判決が下されたのです。広州知的財産法院は、『三戦』が『率土』の著作権を侵害していないと判断し、一審判決を取り消しました。この判決の核心は、「ゲームルール」が著作権で保護されるのかという、ゲーム開発者にとって極めて重要な問いへの司法の姿勢です。本記事では、今回の判決がSLGジャンルのイノベーションに与える示唆と、「自己革命」とも言える大胆な挑戦を続ける『三戦』の戦略について深掘りします。
著作権訴訟が覆した「ゲームルール」の常識
2023年の一審判決では、広州インターネット法院が『中華人民共和国著作権法』の包括規定を適用し、「ゲームルール」(ゲームの遊び方を含む)を著作権保護の対象と認定していました。これは当時の中国ゲーム業界で大きな波紋を呼ぶ画期的な判断でしたが、今回の二審判決でこの判断は完全に覆されることになりました。
二審判決の核心:思想と表現の二分法
広州知的財産法院は、一審法院が「体系的な検討と認定のプロセス」を欠いたまま、電子ゲームを「作品の特性に合致するその他の知的成果」と定義したことは不適切であると裁定しました。そして、著作権法が保護するのは「独創性のある表現」であり、「思想」には及ばないという重要な見解を示しています。
これは国際的にも広く採用されている「思想—表現二分法」に則ったものです。つまり、ゲームにおける遊び方やルールといった「思想、原理、方法」は著作権の保護範囲外であり、保護されるのはそれらが具体的に固定された「表現形式」、例えば美術資源、音楽、効果音などに限定されるということです。
この考え方の背後には、著作権制度の立法目的があります。それは、創作者に一定期間、作品からの経済的利益を独占させることで、より多くの創作活動を促すことにあります。しかし、もし保護範囲が厳しすぎると、後続の創作者の活動が著しく制限されてしまいます。法律は「創作の奨励」と「公共領域の保障」の間で、適切なバランスを見つける必要があるのです。今回の判決は、このバランスを再確認するものであり、ゲーム業界全体のイノベーション推進に一石を投じるものと言えるでしょう。
保守的なSLGジャンルを革新し続ける『三国志・戦略版』の挑戦
今日のゲーム業界において、全く新しい遊び方をゼロから創出することは極めて困難です。むしろ、異なるジャンルの融合(SLGとアクションの融合など)や、既存ジャンルの細分化といった形で進化が進んでいます。これは、SLGゲームの歴史を振り返っても明らかです。そのルールや基礎は、1985年の光栄(現:コーエーテクモゲームス)の『三国志』、さらには1983年の『信長の野望』、そして1979年のSSI社の『Computer Bismarck』、さらにその源流であるテーブルトーク形式のウォーゲームにまで遡ることができます。
どの優れた作品も、先人の経験やアイデアを吸収し、成長してきたと言えるでしょう。この観点から、今回の二審判決を機に、『三戦』という6年間もの間、ジャンル売上首位を走り続けてきた製品が、SLGジャンルのイノベーションにどのような示唆を与えてきたのかを改めて検証します。
「最も大胆」に進化するSLGの旗手
『三戦』は2019年のリリース以来、既にレッドオーシャンとされていたSLG市場において、独自の「敢闘精神」で業界のトップへと駆け上がりました。その原動力となっているのが、圧倒的なイノベーション力と高いゲーム品質です。データによると、この1年で『三戦』はiOSセールスランキングで常にトップ20位以内を維持し、大型アップデート時にはトップ3に食い込むなど、驚異的な実績を残しています。
『三戦』は、プレイヤーを飽きさせないための大規模な刷新を頻繁に行っています。例えば、2021年にはオリジナルの年度シナリオ「赤壁の戦い」を投入し、水戦や火攻めといった新要素を導入しました。風向きを変えて敵を焼き尽くす「火計」は、プレイヤーから「一気に広がる炎が最高に爽快」と絶賛されました。さらに、2024年のシナリオ「潼関の戦い」では、異民族兵種やカスタム戦法を導入し、戦略の幅を大きく広げています。プレイヤーの人気投票では、このシナリオが「SSSS」級の評価を獲得するなど、その革新性は高く評価されています。
さらに、ゲーム5周年を迎えた2024年には、「立体戦争」時代と銘打ち、初めて沙盤マップに「Y軸」(高低差)を導入するという、業界にとっての革命を起こしました。これにより、行軍や戦闘は単なる数値のぶつかり合いではなく、部隊編成に加えて「地形戦略」という新たな次元が加わり、よりリアルな三国志の戦場が再現されています。また、直近の7月には「長安の乱」バージョンで、SLGとしては異例の「巷戦(市街戦)」を実装。従来の広大な野戦から一転、複雑な都市地形の中で迂回や占領施設を巡る攻防が展開され、プレイヤーからは「百万大軍が長安に集結するようだ!」との声も上がっています。
このような高頻度で大胆なイノベーションは、『三戦』をプレイヤーと業界に非常にユニークな存在として印象付けています。SLGゲームのイノベーションは技術的な困難さよりも、ジャンルが持つ内在的な抵抗が最大の障壁となることが多い中、『三戦』は常に大胆な挑戦を続けています。
「自己革命」の勇気の裏に潜むもの
SLGというジャンルは、イノベーションが不可欠でありながらも、大幅な変更を受け入れにくいという矛盾を抱えています。プレイヤーにとってSLGの核となる楽しみの一つは、GvG(チーム対抗戦)です。ここには、チーム内の分業、リーダーシップの戦略的慣性、さらには人間関係の微妙な機微が絡み合っており、多くのプレイヤーが夢中になる理由でもあります。
一つのシーズンが終わると、同盟(ギルド)の管理層は、その沙盤戦闘の根底にあるロジックに依存した効果的な経験と戦闘スタイルを確立します。例えば、戦力が不足していてもアクティブな同盟であれば、粘り強く道を舗装し、戦線を広げ、援護や奇襲の機会を提供する戦術が有効です。この戦術は、「道を舗装するには時間と人員コストがかかる」という前提の上に成り立っています。
もし次のシナリオで、公式が道の舗装コストを大幅に削減するようなルール変更を行えば、既存の同盟戦術は無力化され、同盟内の地位が失墜したり、最悪の場合は崩壊したりする可能性があります。これがプレイヤーの不満につながるため、多くのSLG製品のイノベーションは小規模に留まるか、既に市場で検証済みの成熟した遊び方を導入する傾向があります。
「高低差」「巷戦」、さらには「龍虎賽」「自走棋」といった全く新しい遊び方を導入し、これほどまでに大胆に「自己革命」を敢行する『三戦』のような製品は、ほぼ唯一無二と言えるでしょう。実際、『三戦』はSLGと自走棋を融合させた遊び方をS3シーズンまで継続させています。
つまり、SLGゲームにおけるイノベーション、特に「自己革命」とも呼べるような急進的なイノベーションは、非常に大きなリスクを伴います。制作チームは、プレイヤーコミュニティのニーズや受容度を深く洞察し、「戦略的深み」と「プレイヤーの受容度」のバランスをうまく取ることで、初めて効果的なイノベーションを実現できるのです。ではなぜ、『三戦』はこれほどまでに自らに「メスを入れ」、他社にはないイノベーションを追求し続けられるのでしょうか。その答えは、プレイヤーへの深い理解と、リスクを恐れない開発姿勢にあると言えるでしょう。
まとめ:ゲーム業界と日本への示唆
今回の『三国志・戦略版』の二審判決は、中国のゲーム業界における著作権保護のあり方、特にゲームプレイメカニクスやルールに関する議論に新たな一石を投じました。それは「アイデア(思想)は保護されず、その表現が保護される」という国際的な常識を再確認するものであり、ゲーム開発における創造性と模倣の境界線について、改めて深く考える機会を提供しています。
また、『三戦』の事例は、SLGという歴史と伝統を持つジャンルにおいてさえ、プレイヤーのニーズを深く理解し、リスクを恐れずに大胆なイノベーションを追求することの重要性を示しています。常に新しい体験を提供し続けることで、既存のユーザーを維持しつつ、新規ユーザーの獲得にも成功する。これは、日本のゲーム開発者にとっても、現代の市場で競争力を維持し、ユーザーを魅了し続けるためのヒントとなり得るでしょう。今回の判決と『三戦』の挑戦は、ゲーム業界全体の未来におけるイノベーションのあり方について、示唆に富んだ教訓を与えてくれます。
元記事: chuapp
Photo by Çiğdem Bilgin on Pexels