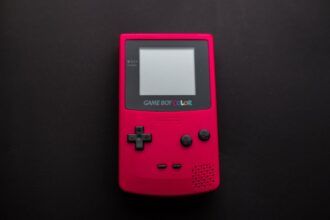ゲーム配信はゲームの知名度や売上を大きく左右する強力なツールとして認識されていますが、近年、その裏側で不穏な声が上がっています。特に日本のゲーム開発者から、「配信者がゲームをプレイして稼ぐお金は、開発者がゲームを作るお金よりも多い」という驚くべき発言が飛び出し、開発者とコンテンツクリエイター間での収益分配の必要性が提唱されています。この問題提起は、デジタルコンテンツ時代の新たな課題として、業界内外で大きな波紋を呼んでいます。
日本の開発者が投げかけた一石:配信者の「ただ乗り」問題
この議論の口火を切ったのは、日本のゲーム開発者である奥田格氏です。彼は自身のソーシャルメディア上で、「私が開発したゲームを有名配信者がプレイし、一夜にして数十万回の視聴を獲得したにもかかわらず、動画内にゲームの販売リンクが一切貼られていなかった。結果として、ゲームの売上には全く貢献せず、配信者は私のゲームに乗じて急速に収益を上げただけだった」と強い不満を表明しました。奥田氏によると、この有名配信者は200万人ものチャンネル登録者を抱えているといいます。
YouTubeなどの動画配信プラットフォームでは、配信者が動画に広告を組み込めばその収益の一部を受け取ることができ、また登録者からの月額費用や「投げ銭」といった形で直接的な支援を受けることも可能です。しかし、これらの収益は、配信者がプレイしているゲームのゲーム開発者には一切還元されないのが現状です。
日本特有の著作権意識と収益分配への提言
奥田氏のこの発言は、日本特有の著作権に対する意識を背景に考えると、より深く理解できます。アニメ、漫画、ゲームといったACG文化を世界に発信する日本は、コンテンツの著作権保護に対して非常に厳格な姿勢を持っています。実際、許諾を得ていないゲーム配信は著作権侵害と見なされるという認識は、日本のゲーム業界ではほぼ共通の認識となっています。任天堂が配信者に対し、事前に配信申請を行うよう求めていることも、その一例です。しかし、日本国外ではこのような見解が強く主張されることは稀で、そのギャップも今回の議論に拍車をかけています。
著名デザイナーの具体的な提案
このような状況に対し、著名なインタラクションデザイナーである深津隆之氏は、さらに具体的な提案を行っています。深津氏は、「ソーシャルメディアが主流の現代において、3年かけて制作した傑作を日々公開し続けることは、自ら3年かけて傑作を生み出すよりも、コストや労力の面で効率的だ」と指摘。その上で、ライブ配信プラットフォームに分配メカニズムを導入し、ゲーム配信による収益の5%をゲーム開発者へ分配すべきだと提唱しました。ただし深津氏自身も、このような制度の実現には、現在のゲーム業界にそれを支持する組織が不足しているため、導入の難易度は高いと認めています。
独立開発者の厳しい現実と業界の課題
配信者からの収益分配を求める声の根本には、独立系ゲーム開発者の深刻な生存危機があります。先日も、ある開発チームが400万ユーロの収益を上げたゲームをリリースしたにもかかわらず、3年後に破産したというニュースが報じられました。この開発者は、パブリッシャーがゲームの収益を他のゲームのマーケティングに流用したと批判。一方パブリッシャー側も、先行投資、多言語ローカライズ、QA、プロモーション、イベント参加など、多岐にわたる費用がかかる現状を訴えています。
奥田氏が指摘した「販売リンクの欠如」についても、調査によると、いわゆる「クラウドゲーマー」(視聴のみでプレイしない層)の73%は「リンクを見ても購入しない」と明確に答えており、彼らは元々ターゲットユーザーではないという見方もあります。ゲーム配信自体がゲームの認知度向上や売上増加に貢献する側面は否定できません。独立系開発者の苦境は、ゲーム配信が登場する以前から存在している問題であり、配信者からの収益分配という提案は、この古くからの傷口をあらわにしたものとも言えるでしょう。
まとめ
ゲームと配信は、本来であれば互いに価値を高め合う関係であるべきです。しかし、今回の日本開発者からの問題提起は、特にインディーゲーム開発者の厳しい生存環境と、デジタルコンテンツ時代の新たな収益モデル構築の必要性を浮き彫りにしました。情報の洪水の中で「注意力」が最も貴重な資源となった今、配信者が新たなプラットフォームやコンテンツへと移行した時、果たして誰がインディーゲームにスポットライトを当て続けるのでしょうか。この問題は、日本のゲーム業界のみならず、世界中のクリエイターとプラットフォームが共に考え、解決策を探るべき重要な課題となっています。
元記事: gamelook
Photo by PNW Production on Pexels