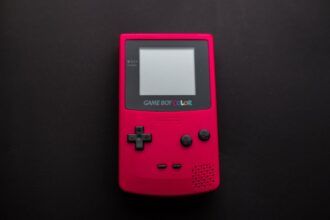先日開催されたChinaJoyで、「日暮鳥工作室」(Sunset Bird Studio)というインディーゲーム開発チームが注目を集めました。彼らが開発している政治シミュレーションゲーム『生育、犯罪と経済』(仮題、現行は『生育、犯罪と経済』、名称変更予定)は、その扱うテーマの敏感さゆえに、業界関係者から「有名なゲーム」として記憶されていました。このゲームは、プレイヤーが新任の省長となり、出生率と犯罪率の維持のため、独身税や出産手当といった政策を5年間で実施するというユニークな内容です。「職業妊婦」の登場など、現実を反映したシナリオがプレイヤーの神経を刺激します。イギリスで設立された彼らが直面する、パブリッシャー探しや表現の自由といった現実的な課題と、それを乗り越えようとする奮闘に迫ります。
異色の政治シミュレーション、その挑戦とは
「日暮鳥工作室」は、創設メンバーがイギリス留学中に立ち上げたインディーゲーム開発スタジオです。彼らが手掛けるゲーム『生育、犯罪と経済』は、プレイヤーが就任したばかりの省長として、5年以内に多様な政策を駆使し、都市の出生率と犯罪率を適切に保つことを目指します。もし目標を達成できなければ、プレイヤーは「強制的に解任」されてしまいます。
ゲームのデモ版では、「独身税」が社会の不安定化を招いたり、「出産手当」が企業による「職業妊婦」の募集といった予期せぬ結果を生んだりするなど、現実社会を想起させる描写が満載でした。これにより、プレイヤーは深い没入感を味わい、社会問題に対する思考を促されます。現在、ゲームは3年ほどの開発期間を経て、初期デモ版からは大幅に内容と遊び方が変更され、より穏やかな印象を与える『凱爾塔黄昏(ケルタ黄昏)』への名称変更も検討されています。
パブリッシャー探しの光と影:業界の支援と「社恐」開発者の奮闘
日暮鳥工作室は、ChinaJoyだけでなく、2024年9月に開催された国内ゲーム展示会「核聚変(Nucleus)」でも存在感を示しました。初期の出展では、まだ調整段階のデモ版ながらも多くの来場者が試遊に訪れ、業界関係者からも注目を集めました。スタジオはイギリス政府からの文化クリエイティブ分野のスタートアップ向けインキュベーション資金を得ていましたが、それも残り少なく、3名のコアメンバーはそれぞれ副業を持ちながら開発を続けています。彼らの最大の課題は、敏感なゲームテーマと、開発メンバーの「社恐」(社交的でない)な性格ゆえの広報・運営経験の不足でした。
しかし、予想に反して、多くのパブリッシャーが彼らのゲームに興味を示し、具体的に改善点を提案するだけでなく、ゲームのテストプレイに協力したり、開発の進捗を定期的に尋ねたり、さらには業界の人脈を紹介したりと、多岐にわたる支援を提供しました。特に、铼3実験室(Rhodium 3 Lab)のようなインキュベーターからは、スタジオの中国への移転に関する法的なアドバイス、政府や民間の助成金情報の提供、Steam新作フェスへの参加時期、適切なプロモーションチャネルの選定など、資金援助以上に「ソフトな支援」が提供されています。大猫头鹰氏(チームリーダー)は、「これは私たちがより長く活動し、落とし穴を避ける上で役立つ」と語っています。
表現の模索とゲームメカニクスの進化
日暮鳥工作室が現在取り組む大きな課題の一つは、ゲームテーマの「敏感さ」をどう表現するかです。初期のデモ版ではアメリカの現代社会を背景としていましたが、特定の状況が中国と類似していると受け取られる可能性を考慮し、全体的な文化背景を第二次世界大戦後のイギリス、1960年代から80年代に変更しました。さらに、登場キャラクターに動物の要素を加えることで、まるで『動物農場』のように、寓話的な表現を通して社会問題を提起する方向へと転換を図っています。これは、「何かを風刺するのではなく、いくつかの事柄について議論する機会を創出したいが、直接的な方法では適切でない、あるいは安全でない」という彼らの思想を反映しています。
また、ゲームプレイメカニクスも大幅に改善されました。初期デモ版の「ゲーム性不足」という課題を認識し、現在は政策の実施だけでなく、具体的な物語ベースの任務や緊急事態(例:政府庁舎爆破事件の aftermath 処理)をプレイヤーに課すことで、より明確な目標とゲームサイクルを作り出しています。これにより、プレイヤーは単なる数値管理ではない、よりダイナミックで物語性の高いシミュレーション体験を享受できるようになりました。
まとめ:社会に問いかけるゲームの未来
『生育、犯罪と経済』、そして新たな名で生まれ変わる『ケルタ黄昏』は、そのテーマの深さと表現の挑戦性において、非常にユニークな存在です。日暮鳥工作室の奮闘は、インディーゲーム開発者が直面する現実的な課題、特に敏感なテーマを扱う際の困難さを浮き彫りにしています。しかし、同時に、彼らが業界内外から得ている「ソフトな支援」は、斬新なアイデアを持つクリエイターが道なき道を進む上での希望でもあります。
ゲームが単なる娯楽に留まらず、社会的な議論を喚起し、プレイヤーに深い思考を促す媒体となり得ることを、彼らは示しています。日本を含む世界のゲーム市場においても、こうした「社科気質(社会科学的気質)」を持つゲームが、新たな価値と可能性を切り拓いていくことでしょう。日暮鳥工作室の今後の展開から目が離せません。
元記事: chuapp
Photo by Julia M Cameron on Pexels